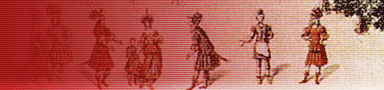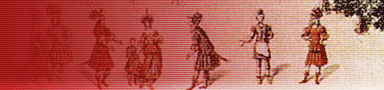研究概要
演劇理論研究(西洋/比較)コースでは、コース全体として、第一線で活躍する著名な演劇研究者による演劇論講座、東京外国語大学教授の谷川道子氏による現代ドイツ演劇をめぐる特別講座、国内外からお迎えするゲストによる各種講演会やワークショップ等を精力的に開催している。これらを通じて欧米演劇の状況や最先端の演劇理論についての知識を共有し理解を深めるとともに活発な討議を行い、研究を推進している。
また、担当教員独自の研究テーマに沿った多様なプロジェクトを設置し、これまで演劇研究では手付かずであった分野を含め、舞台創造の実践家の協力も仰ぎつつ、多彩な研究活動を展開している。
さらに、COEゼミや博士論文執筆経過報告会など特別研究生の研究発表の場を積極的に設けて博士論文執筆の支援に努めているほか、英語ゼミも設置し、国際学会での研究発表や外国語による論文執筆をサポートしている。
演劇理論研究(西洋/比較)コースプログラム
1.COEゼミ【博士論文執筆支援と演劇研究の方法論の探究】
このゼミでは、特別研究生や研究協力者が各自の研究テーマや博士論文執筆の経過について交替で報告し、所属する大学院や研究対象とする地域/言語の枠組みを超えたディスカッションを通じて相互に知的刺激を与え合い、各自の研究の推進と博士論文完成を目指す。また、ディスカッションの中から共通するテーマや問題点を抽出して議論を深め、演劇研究の方法論探求への一助としたい。
2.COE演劇論講座【各国演劇研究の最先端】
(年4回開催予定。日時・講師等詳細はその都度告知する。)
主として欧米演劇を研究対象とする内外の著名な演劇研究者を講師に迎えてご講義いただき、欧米における舞台芸術の歴史と現状について検証し、最先端の演劇理論を研究するとともに、演劇学といういまだ確立されていない研究分野の可能性について探究する。
3.COE特別講座【ドイツ 現代演劇(研究)の構図】
(金曜日午後4時20分‐6時 担当:東京外国語大学教授 谷川道子教授)
昨年度に引き続き、ドイツ演劇研究の最先端でご活躍中の谷川道子氏を講師に迎え、早稲田大学大学院文学研究科設置科目として開講する。
〈講義概要〉「パフォーマンス」という語の流行に象徴される演劇概念の揺らぎはいまや世界共通の趨勢であろうが、そういう中でもドイツ語圏の演劇は、戯曲(ドラマ)と演劇(シアター)の両極を見据えつつ、作品・上演実践においても、理論・研究においても、世界的な影響においてきわめて独自の位置を占めていると言えるだろう。その変容の根源的な様相を、20世紀ドイツ発信のブレヒトとハイナー・ミュラーを主な手がかりに、さらにポスト・ブレヒト演劇から「ポストドラマ演劇」、21世紀の「可能性としての演劇」に向けて、作品と上演実践と演劇理論をトライアングルに見据えつつ、さまざまな角度から考察していきたい。ビデオなどの視聴覚教材も使いつつ、ドイツ演劇が専門でない院生の研究関心ともクロス・リンクできるような視座でともに探っていきたいと思うので、積極的な聴講を期待する。
4.英語ゼミ
(担当:文学部助教授Anthony Martin, 政治経済学部教授Anthony Newell)
(Martinゼミ:月1回土曜日午前中を予定、Newellゼミ:月1回木曜日夕方を予定)
Martinゼミでは、国際学会において英語で研究発表を行うためのスキルを身につけることを目的として、参加者が英語で書いた小論文を持ち寄り、論文執筆と研究発表の訓練を行う。Newellゼミでは、アカデミック・ライティングの方法等、よりベーシックなスキルを学ぶことを目的とする。
5.特別講演会/ワークショップ
国内外の第一線で活躍中の研究者や劇作家、演劇関係者を多数招聘予定。
6.テーマ別プロジェクト研究 ( )内は担当責任者。〈担当者五十音順〉
【比較演劇研究】(秋葉裕一)
ベルトルト・ブレヒトの受容や影響を、さまざまな文化圏、異なった国々、いろいろな時代や社会のうちに眺める。昨年に引き続き、日本におけるブレヒト受容にとくに注目しながら、資料の整理や分析に取り組みたい。ブレヒト受容に積極的に関わった演劇人へのインタビューも実施する。
【ベケット・ゼミ】(岡室美奈子)
2006年にCOE事業として開催を予定しているベケット生誕100周年記念国際シンポジウムに向けて、日本のベケット研究のレヴェルアップを目指す。月1回ベケット勉強会をもち、研究報告を行なう。2005年度中にシンポジウムの研究発表募集が行われる予定なので、応募に向けて具体的に発表論文を英語またはフランス語で作成し、相互批評を行なう。
【現代における西洋演劇の上演とその周辺】(小田島恒志)
日本における外国戯曲の翻訳・演出・演技・観客等、具体的な上演の実例や実践に即した研究を推進し、演劇研究においていかに「上演」を視野に収めうるか検証する。
(2005年度は担当教員特別研究期間のため休止。)
【ポストコロニアル演劇研究】(澤田敬司)
オーストラレジア地域(オーストラリア・ニュージーランド)先住民演劇研究を文献と実際の上演の両面から調査するとともに、日本を含めた世界の諸地域のポストコロニアル演劇についての資料を収集し、個々の作品についての分析を行なう。また、先行研究としてのポストコロニアル演劇理論に対する批判検討を行なう。
【ヨーロッパの演劇博物館と日本演劇関係収蔵資料】(ギュンター・ツォーベル)
ヨーロッパの演劇博物館(民族博物館等を含む)、およびその収蔵物としての演劇関係資料、特に日本の仮面・衣装・芝居絵等についての調査・研究を行う。当面、地域的重点を、東西冷戦終結後その重要性が再認識されつつある、旧東ドイツや東欧諸国に置く。
【フランス語圏演劇研究の現在】(藤井慎太郎)
フランス、ベルギー、カナダを中心とするフランス語圏の舞台芸術の諸相(上演、テクスト、制度、歴史・・・)をできる限り多角的に分析する。日仏演劇協会をはじめとする外部の研究機関や芸術団体とも協力しつつ、第一線で活躍する内外の研究者・実践者を招いて、研究会や講演会を定期的に開催する。今年度はパリ第10大学演劇学科の研究者を9月に招聘する予定である。
【シェイクスピア・ゼミ】(冬木ひろみ)
シェイクスピア、および同時代の劇作家について、最先端の現代批評と緻密なテキスト解釈の両面からアプローチをし、シェイクスピア研究の水準を高める場としたい。ほぼ月一回の研究会を行い、第一線で活躍中のシェイクスピア研究者を招聘してご講演いただくともに、特別研究生や研究協力者による研究報告も行ってゆく予定。
【オペラ/音楽劇の演劇学的アプローチ】(丸本隆)
これまで演劇学の視野から欠落しがちであったオペラ/音楽劇を、演劇研究に不可欠な対象と位置づけ、その学際的・総合的アプローチを試みる。これまで17、18世紀に焦点を定め、舞台芸術と音楽の関係性の考察を重点的に行ってきたが、2005年度はさらに、日本におけるオペラ学の確立を視野に入れた、オペラ/音楽劇に関する根源的・総合的な研究を推進する。外来講師による講演と特別研究生等による研究発表を取り混ぜた、月に2回程度の研究会が活動の中心となる。
【演劇資料の収集と分析】(三神弘子)
上演を視野に入れた演劇理論研究の充実化を図るため、アイルランドを中心に海外の演劇関係アーカイブ資料の収集とその分析を行なう。
■担当者一覧(五十音順)
<教員>
| 氏 名 |
所 属 |
| 秋葉 裕一 |
演劇博物館副館長 ・ 早稲田大学理工学部教授 |
| 岡室美奈子 |
早稲田大学文学部教授 |
| 小田島恒志 |
早稲田大学文学部教授 |
| 桑野 隆 |
早稲田大学教育学部教授 |
| 澤田 敬司 |
早稲田大学法学部助教授 |
| ギュンター・ツォーベル |
早稲田大学政治経済学部教授 |
| 藤井慎太郎 |
早稲田大学文学部助教授 |
| 冬木ひろみ |
早稲田大学文学部助教授 ・ (アーカイブ構築研究コースと兼任) |
| 丸本 隆 |
早稲田大学法学部教授 |
| 三神 弘子 |
早稲田大学国際教養学部教授 |
| 水谷 八也 |
早稲田大学文学部教授 |
| 水野 忠夫 |
早稲田大学文学部教授 |
| 八木 斉子 |
早稲田大学政治経済学部助教授 |
|
<客員研究助手>
| 氏 名 |
所 属 |
| 川島 健 |
早稲田大学演劇博物館・客員研究助手 |
|
|