
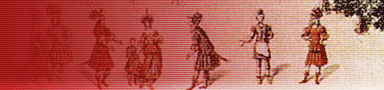
 |
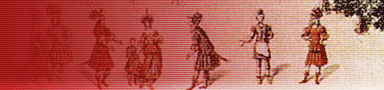 |
| Home > 研究コース紹介 > アーカイブ構築研究(映像) |
|
|
研究概要
映像アーカイブコースでは、以下のようなプロジェクトをもうけて、研究の推進にあたっている。1. グリフィス・プロジェクト 2. 都新聞アーカイブ・プロジェクト 3. その他のアーカイブ作業 ■担当者一覧 <教員>
<客員研究助手>
1. グリフィス・プロジェクト 映画作家としてのデヴィッド・ワーク・グリフィスの重要性は改めて指摘するまでもない。アメリカ映画の、ひいては映画文法そのものの父としてグリフィスが果たした役割は、100年を少し回ったばかりの映画史のあらゆる領域に波及している。本年度より、バイオグラフ期の短編のうち、なかなか接する機会が持てない作品を中心に、年代ごとに順次アーカイブして行く予定である。 ガニングの分析が明らかにしたようにグリフィスがバイオグラフに在籍していた1908年から1913年の間の時期は、映画全体が物語化に向けて大きな揺動を経験した時期である。この時期の作品の分析には、どこまでが個人的な様式でありどこまでが集団的な様式に還元可能なのか、という困難な問いが待ち受けているだけでなく、何をもって物語映画と見なすのか、またどのような技法がそれを可能にしているのか、そもそも何が映画に属し何が属さないのか、という映画の境界そのものを問い直す契機が含まれている。私達は、歴史にその名をとどめる名作から傑作とは必ずしも言いがたい小品まで、彼の名を冠された作品を詳細に分析することで、グリフィス映画の波及力に改めて身を曝してみたいと思う。 2. 都新聞アーカイブ・プロジェクト 初期映画研究において受容論的な研究はますます主流になりつつある。とりわけ関東大震災以前のフィルムがほとんど残存していないという多大なハンディを抱えている日本における初期映画分析において、映画についてなにがしかを語っている資料は特別な重要性を持っている。 初期の映画研究において受容の側面を問うことにはまずもって二つの意義がある。一つは実証的価値であり、作品の残存を見込めない最初期の映画研究にとって、映画について触れている資料は歴史的な再構成のための一義的な重要性を持つ。そして次に挙げられるのは、言説的な価値である。何をもって映画と見なし何をもって見なさないか、というシネマ的事象としての映画の境界は、時代ごとに異なっている。それゆえ、とりわけ映画の境界が常に流動的であった時期に映画について触れている資料は、再構成されるべき対象を導き出すだけでなく、再構成そのものを可能にする能動的な判断基準を提出する。私達はそうした二重の機能を持った資料をとおして、論じられている作品の内容だけでなく、そもそも何が映画と呼ばれていたのか、その社会的・美学的価値はどこにあると見なされていたのかを順次明らかにして行かねばならない。 私達はそうした作業の出発点として、都新聞のアーカイブをスタートした。同紙は明治17年に「今日新聞」として創刊され、同21年に「みやこ新聞」、22年に「都新聞」と改名されついで昭和17年に「東京新聞」と名を改めて現在に至る。本プロジェクトではとりわけ1900年代後半から1910年代の言説に焦点を絞り、映画に関して少しでも触れている記事は残らずアーカイブする計画を立てた。もちろんその後には収集された資料の分類・秩序立ての作業も順次行っていく予定である。こうした作業を通して、闇に沈んでいた日本映画の黎明期にゆっくりと光が当てられていくことになるだろう。 3. その他のアーカイブ作業 上記のプロジェクトに属していなくとも、歴史的な資料的価値を持つフィルムは、そのつど復元し研究対象とする予定である。アーカイブ部門ではこれまで一本のフィルムの復元を終え、その研究成果をイタリアのボルデノーネ無声映画祭で発表する予定である。 |
| | Home | 研究コース紹介 | 演劇研究センター紹介 | 特別研究生 | WEB会議システム | 研究活動 | |