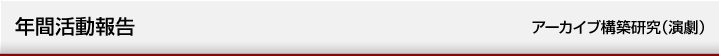
1. ���ҊG������
|
(1) �����͊�b�f�[�^�̓���
WEB��̌����ΏۂƂȂ�A�����m�F���\�ɂ��邽�߂̊�b�I���ڂ���͂����B
�E���͑Ώہ@�V�K��������A�G�t�ʕ��ނ̂����u�����v�E�u���̑��̊G�t�v�̍�i
�E��ȓ��͍��ځ@���i�撆�̕����j�^�𖼁E���Җ��^�ʒu�i���я��j�^�G�t��
�E���͌����@��1070��
(2) ���l�ؖ��ҊG�̍l�E����
��L�̊�{�I�����̊m�F�ɉ����A��X�̉̕���ԕt�A���ҕ]���L�A�䒠���ɂ������ĔN��l�������Ȃ��A�u�ǂ̉��ڂ̂ǂ̏�ʂ�`�������̂��v�܂ł����B���ꂼ��̖��ҊG�ɂ��Č����ȍl�E�����������A���ʂ��f�[�^�x�[�X�֓��͂����B
�E�Ώہ@����̐�L���̍�i
�E��ȓ��͍���
���i�撆�̕����j�^�𖼁E���Җ��^�ʒu�i���я��j�^�G�t���^�Ō���^�Ō����^
������́^���t�^����i���{��j�^������^���s�N���E�㉉�N�����^�n��^����^
�O��^�O���݁^�ꏇ�^�ꖼ�^�����^������݁^���Ȃ̎�ށ^�n�����ށ^���
�E���͌����@��200��
(3) ���ҊG��������̊J��
��L�l�ؐ��ʂ̕E�m�F�̏�Ƃ��āA����1��A���������قɂ����ė����J�Â����B
2002�N11�����2003�N10���܂ŁA2003�N2���E3���������āA�v10��J�ÁA�e��12���̉�����o�Ȃ����B
(4) WEB���J�p�摜�f�[�^�x�[�X�̊g�[
�V�K��������Ȃ�80�_�̉摜�f�[�^��lj������B |
2. ��ڗ��H�ȃf�[�^�x�[�X���̌���
|
(1) ���R�����q�������W�`���v�߃R���N�V�����̃f�W�^�������̊m�F�E���́E�f�[�^����
�E���͍���
�@���ځ^�ꖼ�E�i���^���t�ҁ^�^���N�����^���l�^�ҏW�w��
�E���͐��@CD�|R��150��
(2) ���n����ߘ^������
�E���a47�N�̏W�����̈ꕔ�ɂ��āA���������ُ���̓c����݂��������e�����������Ȃ��A�u���������Z���^�[�I�v I �v�Ɂu����c��w���������ّ��@���n�Ï�ڗ��^�������ژ^�i1�j�v�Ƃ��ĕ����B
(3) ����ߐl�`��ڗ��̓`����r����
�E2003�N10��4����G�u���ɂ����āuCOE���J�u���@����ߐl�`��ڗ��v���J�ÁB���������������ƐV�������n�̐l�`�������ق��A�����ɂ��u�����G�X�q�܁v�̌��J�㉉�A���^�������Ȃ����B |
3. �f�W�^���E�A�[�J�C�u����
|
3-1. �ߑ㉉���㉉�L�^�f�[�^�x�[�X�\�z
���v���W�F�N�g�ł́A���������ُ����̐�O�i�吳���N�`���a15�N���܂Łj�̏㉉��������ɁA�㉉�L�^�f�[�^�x�[�X���\�z���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A���̊�b�I��ƂƂ��āA2003�N�x�̓v���O�����E���炵���̏㉉�����ɂ��āA�N��E���ځE���ꓙ�̃f�[�^�𒆐S�ɍl���A���ꂲ�ƔN�㏇�ɐ����E���ނ����B�܂��A�����E���ލ�Ƃƕ��s���āA�f�[�^�x�[�X�̊�{���ڂɂ��Ă����������B
�E��Ɠ_���F��400�_�i�T�Z�j
�E�ߑ㉉���㉉�L�^�f�[�^�x�[�X�̊�{���ځi�������j
�㉉���IDno.�E�㉉�N�E���ԍ��i���͏��j�㉉��̖��E���ږ��E�������E�ꏊ�i��݁j��E���o�i��݁j�|��E�r�F�������l���炵�E�v���O�����E�����E�`�P�b�g�E�|�X�^�[�E�ʐ^�E��{�E���̑��Җ��E���͎Җ����̑�
3-2. ����\�y�E�����㉉�L�^�f�[�^�x�[�X�\�z
���v���W�F�N�g�ł́A���������ُ����̌���i�吳���N�ȍ~�j�̔\�y�E�����Ɋւ���㉉��������ɁA�\�E�����㉉�L�^�f�[�^�x�[�X���\�z���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A���̊�b��ƂƂ��āA2003�N�x�͐������鉉���㉉��������\�y�E�����Ɋւ���㉉�����ނ��邽�߂̐�����Ƃ��s�����B�܂��A�����E���ލ�Ƃƕ��s���āA�f�[�^�x�[�X�̊�{���ڂɂ��Ă����������B
�E��Ɠ_���F��630�_�i���A�\�E�����㉉�����͖�170�_�B�T�Z�j
�E����\�y�E�����㉉�L�^�f�[�^�x�[�X�̊�{���ځi�������j
�\�E�����㉉���IDno.�E�㉉�N�E���ԍ��i���͏��j
�㉉��̖��E���ږ��E�����E�������E�ꏊ�i��݁j
�V�e�E���L�E�c���E�A�C�E�A�h�E���A�h�i��݁j
�J�E���ہE��ہE���ہi��݁j
��ҁE���
���h�E�\�^����
���炵�E�ԑg�E�v���O�����E�����E�`�P�b�g�E�|�X�^�[�E�ʐ^�E���̑�
�Җ��E���͎Җ�
���̑�
3-3. ���{��{�f�W�^����
(1) �����T�v
�����T�v�ɂ��Ă͔����́w���������َ������̂�����x�ɏڂ������A���̉�����ӂ܂������ł��炽�߂ĊȒP�ɂ܂Ƃ߂�B���������قɂ͐�O�E�풆�E���ɂ܂����莞�̈א��҂ɂ�錟�{������{��������������Ă���A�������u���{��{�v�Ƒ��̂��Ă���B�{�v���W�F�N�g�ɂ����ē��ʌ����ΏۂƂ���̂́A�~�V�K����w����1985�N�����������قֈڊǂ��ꂽ������8,000�_�́u��B�n�����ƌ��c�̌��{��{�Q�v�ł���B�����m�푈�����GHQ�ɂ�錟�{��{�ŁA�����s�ɂ�������3�n�挟�{�ǂɕۊǂ���Ă������{�p��{�̕��{���A��̏I����ɃA�����J�֎����^��A���̌�~�V�K����w�ֈڑ����ꂽ���̂ł���B�قƂ�ǂ��r���ɃJ�[�{�����ʂŁA�ѕM�����̂��̂�����B��_���t���琔�\�t�ŁA�\���͌r�����邢�͌��������Ă���A�R�ŊȒP�ɒԂ����Ă���B�������e���ŒԂ����ȈՂȂ��ߗ��i�݂���B���e�I�ɂ͒n�����ƈ�����L�̌җ����A���P�����I���ꂪ�唼�ł��邪���|���A�̕���A���y�A���x���A�����m�a��Ȃǂ�����B
(2) �A�[�J�C�u�\�z
�A�[�J�C�u�\�z�̋�̓I�ȍ�ƂƂ��ẮA�܂����i�K�Ƃ��ď����f�[�^�ƌ������̏ƍ����s���Ώێ����Q�̑S�̑����c���ł���悤�ژ^�쐬�ɂƂ肩�������B�ꕔ�����͂̎����ɂ��Ă͐V�K�Ƀf�[�^�����s�����B���������قł̐�����Ƃɂ��A����̏����I���͂��łɃf�[�^���ς݂ŁA���ڂ́A���A�s�S�A�O��A��ҁA�r�F�A���c
�E���ҁA�\���ҁA���E�s���A�����ʁA�W�������A���e�A�N�����ł���B����̌��c�ⓖ���̋�̓I�ȉ����ȂǁA���邢�͍��ڂ̗��ĕ���W�����������Ȃǂɂ��āA�I���m�\���i�����w���������ٖ��_�����j�A�{�c�ɍK���i�����������������|�\�������|�\�����j�ɂ��ꂼ�ꋦ�͂����ł���A���ꂩ�炳��Ƀf�[�^�̐M���������܂�Ǝv����B
��ƒ��Ɏ���ɖ��炩�ɂȂ��Ă������_�Ƃ��ẮA�܂���{�����Ƃ��ꂽ���s���Ƃ��ꂽ���ɂ��āA���ʂ�������Ƃł���B�قƂ�ǂ̑�{�͌��{����ь��{���T�C���̕����������Ă���A�\���ɁhOK�h��hsuppressed�h�Ƃ����������������c����Ă���悢���A����������ꍇ�A���Ɂ~��Ƃ������L���Ŕ��f���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���{����������ꂽ�o�܂ɂ��Ă͍��̂Ƃ���s���ł��邪�A�I�����ɂ��ƁA�u�A�����J�{�y�����đD�ւɍڂ��邽�߂ɍ�����ۂɂ͐���͍s���Ă��Ȃ������v�B�����K������������8,000�_�ȏ�ƁA�܂Ƃ܂������ʂł��邽�߁A����������L���͂�����x�ތ^�����\�ƌ�����ł���B
�܂��ʂ̖��Ƃ��āA�u��O�����v�A�u�V���v�A�u�̕���v�A�u�w�������v�A�u�g�������v�Ȃǂ̃W�����������ɂ��ẮA����ӓI�ł���ʂ��ۂ߂Ȃ��B����W���������ڂɂ��Ă͗p�ꓝ�����܂ߍČ������Ă����B
���i�K�Ƃ��Ėژ^�f�[�^�쐬�ɕ��s���đ�{�S���̕\������ь��{���Ȃǂ��f�W�^���B�e���Ă���A��3,000���܂ŎB�e�����������B�\���ɓ��e��W�����Ă��邽�ߌ����_�őS�ł��B�e����K�v�͂Ȃ��Ɣ��f�����B�ŏI�I�ɉ摜�Ə����f�[�^�����т��A�f�[�^�x�[�X�Ƃ��ĉ��������ف^���������Z���^�[WEB�T�C�g��ɃI�����C�����J����\��ł���B���p�҂̓C���^�[�l�b�g�ɐڑ�����������PC�Ō���������s���A�Ⴆ�Ό��ʁA���c�ʁA�W�������ʂȂǂɒ��o���A�����I���ƕ\���摜����ׂĉ{�����邱�Ƃ��\�ƂȂ錩���݂ł���B
(3) ������

�u��̊��̉����ƌ��{�v
2003�N10��28���i���j19�F00�`20�F30
����c��w������c�L�����p�X6����3�K�@���N�`���[���[��
�u�@�t�F�I���m�\���i�����w���������ٖ��_�����j�A
������F�{�c�ɍK���i�����������������|�\�������|�\�����j

�u��̊��̉����ƌ��{�v�U
2003�N11��28���i���j18�F00�`19�F30
����c��w������c�L�����p�X6����3�K�@���N�`���[���[��
�u�@�t�F�W�F�[���Y�E�u�����h�����i�n���C��w�����w�������j

��3���{�ǂ̊J�ݓ���������ǂ��A���{�Ǖ��̓��܂ŋΖ������o�������A�I���m�\�����u�t�Ɍ}���A�����̏Ȃǂ����b���������@���݂����B������́A���������ُ������{��{�̑̌n�I�����ƃf�[�^�x�[�X���ɍŏ��Ɏ��g�܂ꂽ�A�{�c�ɍK���ɂ��肢�����B���e�Ƃ��ẮA�I�����ɓ����̂��Ƃ����b���������A�K�X�����肩�玿������ނƂ����`�ōs��ꂽ�B�20�œ��ǂ���A�ŏI�I�ɂ͓��{�l�̒��ōŏ�ʂ̐E���ƂȂ�������A���ǂ̍ō��ӔC�҂������ČR���Z�Ƃ̐E���𗣂ꂽ�𗬂ȂǁA��B�n��̉��������܂߂��b�͐s�����A�����\�肵�Ă����I�����Ԃ��z������������B
�X�Ɏ��͕������{�ǂ����E���U���鎞�ɍ쐬���������̐E������ȂǁA���ɋM�d�Ȍ������𑽐����Q����A�Q���ґS���ł��̎����������B�r���A������[�߂�ꏕ�Ƃ��āA�������{��{�̌��{��쐬�r���̃f�[�^�x�[�X�Ȃǂ��ꕔ���J�������A�폜������̐Ղ����X�������ۂ̎����Ƃ����āA�Q���҂̊S�������A����̗��p����J�����Ɋւ��Ă̎�������������B�����̗[������ɂ�������炸�A��w�@�����n�߉����ȊO�̕���̕����Q������A���^�������ɂ́A���{�ǂł̐l��I�ȑg�D�\����A�����̈�ʓI�Ȑ����u���Ɖ����Ƃ̊W�ȂǁA���ɐ��I�Ȏ��₪�o����A�����ΏۂƂ��Ắu��̉�����v�ւ̊S�̍��������炽�߂Ď��������B
3-4. �����V�������L���f�[�^�x�[�X
���������قɂ́A���a18�N���畽��10�N�܂ł̓����V���̉����L���������ۑ�����Ă���B�������_�����ł��錴���͋ߔN���ɗ��i�݁A�R�s�[�Ȃǂ̗��p�ɑς����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���̂�����ł���B�����ō���ACOE�̃f�W�^���A�[�J�C�u�\�z�̈�Ƃ��āA�����̉����L�����f�[�^�x�[�X�����A����ɏd�v�Ǝv����L�����s�b�N�A�b�v���āA�X�̃f�[�^�ɉ摜��Y�t����Ƃ������݂��n�߂��B�i�Ƃ��Ă��鍀�ڂƂ��Ă͔N�����A�����W�������A�L���^�C�g���A���c�E�l�����ł���B�Ȃ��e���r�ԑg���Ɋւ��ẮA���ݓ��͒��̔N��ł́A�e��e���r�ԑg�Љ�G�������s����Ă���A��������������\�Ȃ��߁A���W�E�Љ�L���݂̂̃s�b�N�A�b�v�Ƃ��Ă���B�j
�S�W�������ƂȂ��1�������ł�400���߂��Ȃ��A�L���̐������Ɠ��͂ɂ�����x�̏K�n���K�v�Ƃ����ĈӊO�Ɏ��Ԃ�������A���i�K�ł�6��������2600���̃f�[�^����͂����Ƃ���ł���B�������A�W�ς��Ă݂�ƌ|�\���ɂ͒�]�̂��铌���V�����������āA�����Ȍ��c�̌������m�₻��ɑ��錀�]�ȂǁA���ł͓����Ȃ��L�����ڂ��Ă���̂ŁA���ꂩ��̋ߌ���̉��������ɂƂ��Ă͔��ɗL�v�ȏ�ɂȂ�Ǝv����B
���N�x�͓��ʃf�[�^���͂ɐ�O���A���N�x��������I�ɉ摜�̓Y�t���J�n���悤�ƍl���Ă���B�����I�ɂ́A���������َ����̃`���V�E�p���t���b�g�̃f�[�^�x�[�X�Ƃ������N�����A�����ʂ�L�x�ɂ��Ă䂫�����B
|
 |
|



